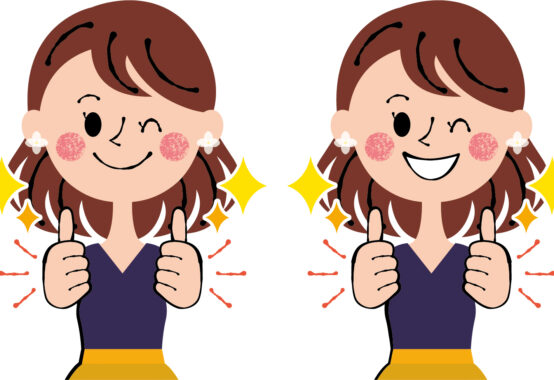■スタッフの成長にブレーキをかけてしまった店長の思い込みとは?-3つのケースから
1.この枠の中に入ることが成長への道!
ブランドのコスメを販売しているある店長は、自分の育成スキルに自信を持っていました。実際これまで何人もの日本人の美容部員を成長させてきた実績もあります。しかしその自信が大きく揺らぐ事態が発生しました。きっかけはインバウンドのお客様増に伴い複数の外国人スタッフが入ってきたことです。やる気と自信に満ちた店長は、外国人スタッフに対して「日本のおもてなしができるよう、所作から日本語の敬語までことこまかに教えてあげることが責任であり、本人のためにもなる」という強い想いで、一挙手一投足をチェックしながら「日本ではこのやり方でないとクレームになります!」と細かく注意をしていました。しかし、熱心に教えている割には外国人スタッフの所作にはどうしてもぎこちなさが残ったり、抜け・ミスがあったりで、日本人スタッフと同じように成長しないフラストレーションが募っていきました。最終的には「外国人スタッフは困り者だな・・」という想いが芽生え始めました。且つ、その空気が当の外国人スタッフ達にも伝わり、一人、二人と辞められてしまいました。せっかくの親心が仇になってしまって、店長自身どこで歯車が狂ってしまったのか、悩んでしまいました。どうすればよかったのでしょうか?
この場合、まずは「海外からのお客様にせよ、日本人のお客様にせよ、お客様が外国人スタッフに、何をどのレベルまで求めているか?」をまず明確にしたうえで、優先順位をつけて1つずつスキルアップしてもらうことが必要でした。まずは、身だしなみ、笑顔、基本の挨拶、ミスのないオペレーションを徹底し、その上でニーズを聞く、提案する‥と続きます。「おもてなし」と言っても概念が広すぎるのと、日本人スタッフでも難しいことがたくさん含まれています。ですから、理想となる”おもてなし”とは?をまずは分解して、ステップ化することが大切です。が、そこにもまた落とし穴があります。すなわち、枠はめです。
外国人スタッフは日本人スタッフ以上に「国籍」「語学レベル」「育った環境」「接客に対する考え方」「求めていること」「慣習」等、ばらばらです。当然それによって物事の捉え方も大きく違ってきます。その違いを踏まえて、期待値、教える事柄の優先順位や、ステップアップ段階も設定する必要が出てきます。それを画一的に「うちでは配属されたらまずこれをやって、次に~してください!それが当たり前ですから!」(暗にそれ以外は許さない、というニュアンス)というのは、店舗側はマネージしやすくても、能力開発という点では画一的な枠にはめることによる限界がでてきます。それが離職にもつながってしまうのです。
できる店長は、同じエネルギーをかけるのであれば、「日本人らしくやってください」と枠に追い込むのではなく、むしろ様々な国のスタッフを通して「その国の風習・常識・接客のあり方」を知り、貪欲に自分たちの接客に取り入れられるヒントを掴むチャンスにしています。且つ、得意な点をそれぞれ活かして、接客を通してお客様を楽しませるには何が大切かを共有し、まずはそれにチャレンジしてもらっています。そうやって何事も柔軟に前向きなチャンスととらえ、知識・ノウハウを広げることができる店長こそが、今後さらにダイバシティが進む中でインクルージョン(受容・包括・一体性)を実現し、存在価値を発揮できるのだと教えられます。

2.指導とは、できていないところを直すこと!
店長であればスタッフには高い基準で行動してもらいたいと思うことは自然です。しかし現実には、スタッフのスキルの格差や行動のばらつきが目につき、「~してほしいのに・・」と心の中でつぶやくこともしばしばです。ただしその際「できていないところをできるようになってもらう」ことばかりに目が行ってしまうと本当の意味で強いチームを創ることはできません。なぜなら、スタッフは指摘を受けて1つ1つのことを改善はできても、「あなたはここができていない」が刷り込まれることによって、”とりあえずできるレベル”がゴールとなり、そこからさらに上を目指すパワーがスタッフの内側から生まれてくることは少ないからです。できていないことができるようになることも重要ですが、「できている点」の中でもさらに伸ばすとより効果につながるポイントを見つけ、そこに注力させることで、まだ眠っている力を引き出していく。それが育成といえます。
ただ、その強みが人によって違う、伸ばし方も人によって違う、且つその違いが大きくなっているのが今の時代。
できる店長は、理想の店舗を創るには、誰のどういう強みをどう活かしたら良いかを考えてデザインしようとします。
一番効果的なのは、役割・仕事の任せ方の工夫です。この業務を通じて、どういう力をどう発揮してほしいのか?をきちんと伝える、また、誰にどうサポートしてもらうことが、さらなる効果につながるのかを考えて任せる。それは例えば~というコンセプトの部屋にしたい、と思った際、必要な家具の素材・カラー・機能を考慮し、配置することでトータルとして調和させるというデザイン力に通じます。そういう点で、できる店長と話していると、全体構想を描く力と同時に、一人一人のスタッフの強みと課題を見抜く観察・洞察力の鋭さに驚かされることがしばしばあります。
3.風通しが良く、居心地がよい環境であればスタッフは辞めない!
最近はパワハラ等のリスクもあって、スタッフに強く言って離職されたり、モチベーションが下がっては意味がない、とばかりに「はっきり指摘しない、できない」という店長の悩みも多く聴きます。「スタッフの話を傾聴し気づかせる」というコーチングの名の下に、店長が言いたいことをひたすら我慢してスタッフの言い分につきあってしまっているケースもあります。
「そうすることでリスク回避もできるし、やる気になってくれるのでは・・・」という期待や幻想を抱き、問題を先送りしてしまうのです。
しかしそれは逆に、スタッフ自身が本来持つ「問題への対応力」や「自ら壁を乗り越えようとチャレンジする」「失敗から学ぶ」などの強さを奪うことにもなりかねないのです。
やるべきは、スタッフが本来持つ力を 「ビジネス」というプロの厳しさも求められる世界で どう開花させるかです。
できる店長は、スタッフからそういう力を奪わないように、
*失敗したらきちんと要因を掘り下げて対応策を考える力をつけさせる指導
*ルール違反等に対しては、及ぼす影響や本人の信用に関わる点などをしっかり自覚させる、言い方は優しくても、厳しい姿勢で接する指導
を非常に重視しています。
その研究をしないで、「ちょっと厳しく言ったら泣かれてしまったたから強く言えない」「辞められたら困るから言えない」では、本末転倒と言えます。
コーチングの最大の狙いは「自ら問題解決ができるようにする&行動変容」です。しっかり行動が変わることを見届けられるまでは最低6回はやり方を変えて言う、という安易に問題から逃げさせない指導です。
そうすることで、最終的にスタッフもセルフコントロールができるようになります。
ただその気づきのレベルやタイミングが以前に比べスタッフ個々で多様化しているので戸惑うこともあります。が、いろいろなケースがあるからこそ店長の指導の引き出しを広げる教材となりうるのです。
以上、スタッフの価値観も多様化していく時代に本当の意味で「プロフェッショナル店長」になるためには、部下育成の本質をより深く理解し、自己の指導効果を楽しみに日々研究あるのみです。
最後に、あるできる店長の言葉です。
「店長の役割は木々の剪定をする庭師に似ています。庭師もスキルの差が激しいと言われる仕事です。
たとえば、「剪定(枝を切る)」は、「伸びてきて邪魔だからここを短く切る」というだけなら、誰でもできます。でもプロの「庭師」は剪定の奥深さをきちんと知って対処するため、最終的に、その木々が美しく長く生きられるように、という先々のことも考えて対応している、とのことです。
正しい剪定によって、大切な木が豊かに茂るように、わたしたち店長の対応によって、本来力強く成長したい、というそもそものパワーを引き出せたらいいな、と思いながら日々格闘しています」

★関連記事→あなたの店舗のチームワーク。スタッフはどう見てる?~スタッフの生の声から:ブランド店長問題解決講座(80)
★お勧め本→Kindle&ペーパーバック出版!【ラグジュアリーブランド店長として輝き続けるための 5つの問い】9月1日出版,『新しい店長のバイブル~業績を上げ続ける店舗はこうして創る!』(PHP)
★ラグジュアリーブランド研修の情報はこちら→ラグジュアリーブランド研修