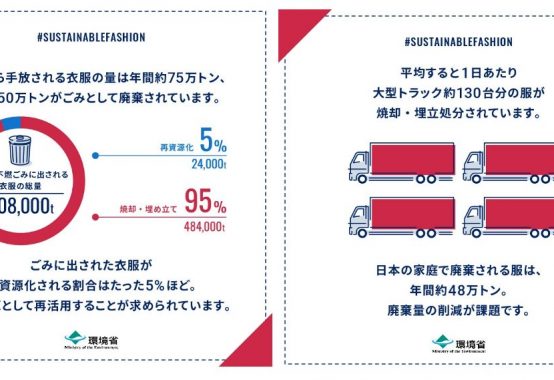■店舗のチームワークを阻害する3つの壁
店舗としてのチーム成果を常に問われる店長の立場からすると、どうすれば今以上に結束して共通目標にチャレンジできる強いチームが作れるか?また作るだけでなく、それを継続できるか?は非常に重要なテーマです。そこで、逆にチームワークを阻害する特に大きな3つの壁を順にとりあげ、それらをどう乗り越えればよいのか(できる店長は具体的に何をしているのか?)という観点で考えてみたいと思います。今回はまずその1回目です。
注意いただきたいのは、ここで挙げる阻害要因は、あくまで”スタッフの立場から見て”が前提です。店長としては「これだけちゃんとやっているのに‥」という想いがあるかもしれません。が、大切なのは相手の立場、視点にそれがどう映っているか?です。一度、自分の視点を離れ、スタッフの視点に立って店舗を点検してみると、意外にチームワークをよくするヒントが足元で見つかるかもしれません。
■そもそも店舗の共通目標の提示・共有の仕方に問題はありませんか?
□自分はなぜここにいる?がスタッフに正しく認識されていますか?
チームとは「共通の目標」を達成するために活動しあう複数のメンバーを指します。となると、「店舗予算は会社が示した目標であって、私の目標ではない」「チーム目標を達成しようがしまいが、私には関係ない」から始まり、「チームの目標自体を良く知らない」「言われたことをやるためにここにいる」という気持ちでスタッフがそこにいるとなると、実はそもそもチームとはいえないのです。もちろん、共通の目標さえあればいいわけではありません。が、まず大前提として、「共通の目標の達成のために自分はここにいる」ということを一人一人が自覚して仕事に取り組んでいますか?というところからチェックしてみましょう。逆に、配属されてきたスタッフだから自然とチームの一員、と安易に受け止めるのではなく、最初の段階で「ここで一緒に働くということは‥私たちが目指しているのは・・・」からまず店長がしっかり伝えているかどうかが重要な分かれ目です。
さらに、あなたが掲げた店舗の共通目標はスタッフから見て以下の条件を満たしているかどうか振り返ってみましょう。
□「何にどう取り組めば目標が達成できそうか?」(what,how)というたたき台を提示し、スタッフのアイディアを入れて「それなら達成できそうだ!」と確信させていますか?
当然店長だって会社からチャレンジングな予算を示されれば、「さて、どうやってそこに到達すればよいのか?」と悩むことはしばしばあります。その道筋が最初から見えていれば誰も苦労はしません。ただ、リーダーの仕事の非常に重要な部分が、先行き不透明な中で、「何にどう取り組めばこの高い目標達成が見えてくるのか?」ーその成功への道筋を考え抜き、スタッフに”それなら行けそうだ!”という成功への期待感を醸成することです。すなわち「可能性への挑戦」です。さもなければ、皆好き勝手な道を選び、チームの結束は期待できません。
そのためには、まずは「これなら行ける!」と店長自身、確信を持つ必要があります。且つ、それが単なる楽観主義、妄想、と思われないよう、スタッフや関係者にある程度納得してもらえる材料集めが必要です。お勧めとしては、まずは徹底的にポジティブな材料を探し、書きだして並べてみる、ということです。たとえば
①自店を取り巻く環境(市況、トレンド、お客様の嗜好、競合、取引先の動きなど幅広く)の中で、自店にとって今期プラスに働きそうな要素は何か?を多面的に洗い出す
②これまでの実績、他店との比較なども通して自店の強みを多面的に洗い出す(昨年のデータも参考にする:中心顧客層、リテンション度合とその要因、どういう時どういうモノが売れるかとその理由など)
③会社・部門全体の取り組み、ツール、支援等で、自店にとってプラスに活用できそうな要素は何か?を洗い出す
④各スタッフのさらに伸ばせそうな要素は何か?を洗い出す
⑤自店の体制・役割などを変える、進化させることでプラスに働く要素はないか?を探す
⑥他社・他店の成功事例とそのノウハウを集める、などなど
ここまで来てお分かりのように、いきなり情報収集する、というより、気づいたときに気づいたこと、たとえば「次に活かせる成功要因」「培うことができた強み」「可能性が見えたこと」などを、きちんと書きだしておくと非常に参考になります。書く、という行為は振り返りもできるうえ、他者との共有にも役立ちます。あとは、店長自身の覚悟をもって「これにこう取り組めば、いけそうだ!やってみよう!」と意思決定することです。ただ、一人の考えでは盲点も多々生まれますので、上司、スタッフ、他店の同僚、などの意見も聞いてみることも大切です。
ただし、それも人を選ぶ必要はあります。ネガティブな思考の人と話をする中でせっかく描いた可能性がしぼんでいってしまうリスクがあります。自ら疑心暗鬼になると、良いアイディアも生まれにくくなることから、この段階ではできるだけ、アグレッシブな人の意見を聞いて自分の視野を広げることをお勧めします。私自身の体験でも、覚悟を決めたうえで、リスクになりそうなことを洗い出すという手順を踏むと「確かにリスクはあるけれど、こうすればできるかな」と思考を前に進めやすくなります。

□共通目標達成のために一人一人に対し「何を、いつまでに、どのレベルまで(what,when,how much)」やらなければならないかを提示していますか?
年間の共通目標達成のために、日・週・月を通して、具体的に誰が、何をどれだけ、あるいはどのレベルまでやる必要があるのかを明確に示さないと、スタッフも日々何に向けて頑張ればよいのかわかりません。ただし、「月次や日割り予算は個人に振り分けてある」で終わっているケースも見受けられます。それで本当に数字を達成し続けられるか?と言われれば疑問です。数字を達成し続けるためには、(他社・他店と比較されたとしても)お客様に自店で喜んでお買い上げいただけるレベルの製品・サービスを提供する体制・スキルが不可欠で、そこに焦点を当てて、スタッフ個々が取り組むべき課題を明確にし、ドライブをかける必要があります。あれもこれもやらなければと、ただ忙しく走り回ることを良しとするのではなく、決めた課題に取り組み、やりきることこそがチームの一員としての「責任」であることをスタッフと共有し、その進捗管理をチームとして行うことが重要なのです。
ある店舗では、決定率を●月までに●%に高めるを目標に、月次のチームでの具体的な取り組み課題(何を、どのレベルまで)を設定し、手順を踏んでスキルアップを図りました。計画通りに数字がついてこない月もありましたが、あきらめずにスキル定着化のためのトーク共有、一客一客の振り返り、個別フィードバック、ロールプレイング、フォロー接客を重ねることで、目標の半年後には、全スタッフ中8割が、目標の決定率を達成。店舗としても達成することができ、且つそのレベルを維持できています。
□「なぜそのレベルまで頑張って達成する必要があるか?(why)」を落とし込んでいますか?
会社が掲げる目標は大半がチャレンジングです。そうしないと市場シェアをあっという間に失ってしまうリスクがあるからです。当然、目標達成のためにはスタッフ一人一人も昨年と同じレベルではなく、何かしらストレッチし、成長しなければなりません。
しかし、昨今「ワークライフバランス」というキーワードが広がったことで、一部のスタッフの中には「仕事は無理のない範囲で、ほどほどでOK。プライベートを犠牲にすることは良くないこと」という勘違いを生んでいるケースもゼロではありません。チームメンバーの中にそのような誤った考え方が入り込むと、その分誰かにそのしわ寄せが行き、共通目標達成が難しいどころか、不公平感が生まれてチームが崩れかねません。
ですから、「なぜ去年よりも、今年これだけチャレンジして頑張る必要があるのか?」を根拠を明確にしつつ示し、説明する必要があります。最終的に、人は成長すればしただけ、より選択肢が広がり、目先だけでなく将来の可能性につながることも含めて気づいてもらうことも大切です。
且つ、現実に人や時間の制約がある中で「そのために新たに始めること、やめること、改善すべきこと、磨くべきスキルは?」等について、情報交換しつつ、スタッフ自身にしっかり考えてもらうことが重要です。
□仮想敵を創ってゲーム感覚で競う等、目標へのチャレンジを楽しめる工夫をしていますか?
スポーツチームが結束しやすいのは、常に戦うべき相手、すなわち「敵」がいるからと言えます。戦う相手に対し、どういう作戦で闘えば勝てそうか?を上記のような要素を踏まえて一試合、一試合意識し、必要なことは即取り入れ進化していきます。であれば、ビジネスでも良い意味でゲーム感覚で仮想敵を設定することで、常に比較しながら何ができるかをチームメンバー全員で考え、すぐに取り入れ、成果を振り返るというサイクルに持ち込めます。それは例えば、似たような位置づけにある同じ会社の他の店舗でも良いでしょうし、ある程度情報が取れる競合店でもよいかもしれません。あるいは、チームを複数に分けて、小単位で競い合うことも一つです。いずれにせよ、そういう張り合いがあった方が、結果的にチームワークはうまく行きやすいと言えます。ただ、あまりに長い期間だと、どうしてもマンネリ化してしまうため、長くても数か月単位で区切って棚卸すると効果的です。もちろん会社のインセンティブが絡むキャンペーンで「●位以内に入ろう!」という共通目標なども有効活用できます。その際も、「どうせうちは‥」と最初から負け組意識になったり白けてしまっている店長を見かけることもありますが、みすみすチャンスをつぶしているようなものです。どう面白がってやるか、だけでなく、それを使ってどうチームワーク強化のチャンスにできるかを考えるのが店長の役割なのです。
次回は、3つの阻害要因の②について考えます。
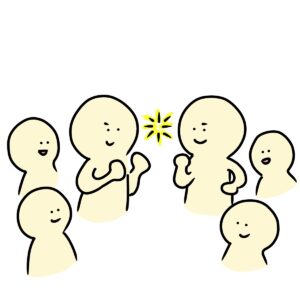
★関連記事→店舗のチームワーク強化作戦!②メンバーの成長を促す役割の任せ方とは?:ブランド店長問題解決講座(82)
店舗のチームワーク強化作戦!③信頼感を高め合うコミュニケーション実践法とは?:ブランド店長問題解決講座(83)
★お勧め本→Kindle&ペーパーバック出版!【ラグジュアリーブランド店長として輝き続けるための 5つの問い】9月1日出版,『新しい店長のバイブル~業績を上げ続ける店舗はこうして創る!』(PHP)
★ラグジュアリーブランド研修についてはこちら→ラグジュアリーブランド研修シリーズ