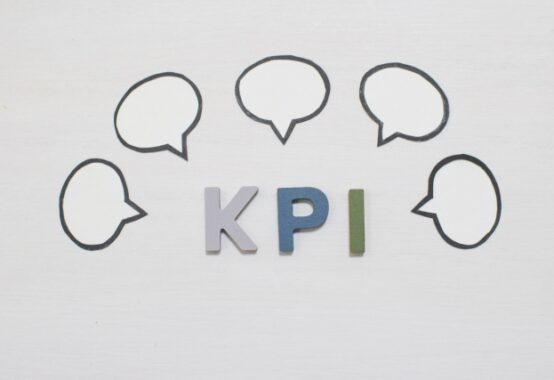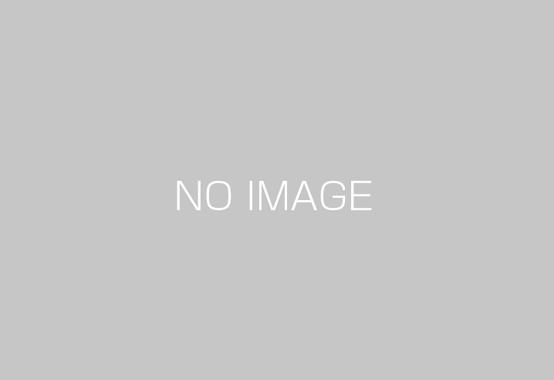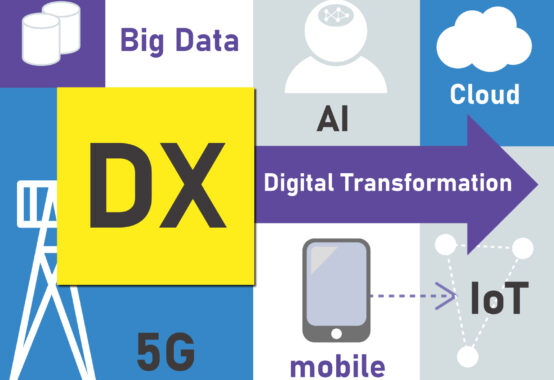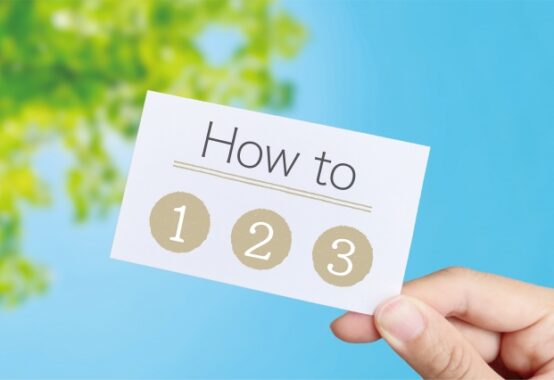店舗のチームワーク強化作戦!シリーズ(店舗のチームワークを阻害する3つの壁とその乗り越え策!)
■コミュニケーションは、”3割伝われば上出来”、という前提に立っていますか?
コミュニケーションは、日本語では「意思疎通」と訳されますが、単なる言葉のやり取りではなく、言葉等を使いながら「意思(思い、考え)」を正しくやり取りすることです。が、実際にはそう簡単ではありません。正しくやり取りしようと思えば、まずは自分の考えを明確にし、それをきちんと伝わるように組み立てなければなりません。そのうえで、相手の理解度、興味関心度を踏まえ、どうすれば伝わるか?について最良の手段を考え・・となると、非常に労力を必要とします。そこまでやっても、受け止め側のフィルターがありますから、正しく意思を受け取ってもらえるかどうかは分かりません。だからこそ、エグゼクティブやプロフェッショナルな営業担当者達は、ロールプレイングをビデオでとって、自分で振り返ったり、プロのアドバイザーからアドバイスをもらってより正しく伝わる練習をするのです。

これは、店長とスタッフの関係にも当てはまります。店長としては、スタッフに分かってほしいと熱心にアイコンタクトをとって情報を伝えたり、フィードバックをしますが、スタッフ側はともすると店長に対する配慮や遠慮から、分からなくても分かったようなふりをしてしまう、あるいは本当にわかった「つもり」になることもあります。リアクションだけ見れば、質問もないし、うなづいてもくれるから伝わったという安心感がありますが、忙しい日常においては特に、理解してほしいと思うことのせいぜい3割伝わっていれば上出来、というのが意思疎通の実情です。にもかかわらず「忙しくてコミュニケーションをとっている時間がない」となれば、それが2割、1割に低下していきます。となると、「なぜ伝わらないの?」ではなく「伝わらなくて当たり前。どうすれば3割を3割5分、4割に近づけることができるか?」を考えることが共通目標達成に向けて結束しあううえで、必要なのです。
実は、意思疎通のまずさを放置すると、単に言ったことが正しく伝わらない、という問題以上により大きなリスクが生まれます。すなわち、お互いに勝手な「思い込み・先入観・憶測」等が入り込む余地ができ、そこから「店長は~というけど、実際は~ではないか」という疑念、誤解、曲解が幅を利かせるようになり、最終的にはチーム内に不信感がはびこる、というケースです。
実際にある店長いわく、スタッフに「バタバタしていて、なかなかコミュニケーションの時間が取れず申し訳ない」というと、スタッフからは決まって「いえ、店長もお忙しいですから、気にしないでください」という答が返ってきてそれなりに”仕方がない”で済ませていたけれど、ある日従業員満足度アンケートの結果を渡されました。それを見ると「店長はいつも慌ただしく、自分たちに関心を持ってくれていないように感じる」「どうせ相談しても現場を見ていないことも多く、状況をわかってもらえない、だから相談する気になれない」ということが多々書かれていて、非常にショックを受けました、とのこと。「そういうそぶりや気配を感じていれば、私も危機感をもって、忙しい中でももっとやれたことはあったと思いますが、皆いつもポーカーフェイスだっただけに衝撃が大きいです」と落ち込んでいました。いわゆる「分かり合えているはず」「わかってくれているはず」という楽観的な観測が崩れた瞬間だったようです。ただ、逆に言えば、気づけたから良かったようなもので、それを放置すると、店長が何か言っても「どうせ現場を分からないで言っているんでしょ」という不信感が蔓延してしまい、笛吹けど踊らず、という風土が出来上がってしまうのです。
■できる店長が実践している、スタッフとの”戦略的なコミュニケーション”
もちろん時間制約がある中で、無駄にコミュニケーションの機会さえ持てばよい、というものではありません。表面的な会話をしているだけでは、お互い腹の探り合いで終わってしまうこともあります。
ある店長が実践しているのは、長い時間でなくても良いので、スタッフの言動や変化を観察し、事実をもとに「さっき、○○をしてくれてありがとう」「今のお客様に~が売れてよかったね。××というキーワードが響いたと思うので、他のスタッフにもシェアさせてもらうね」などその場で発信することで、スタッフが笑顔で返してくれるようになりました、とのこと。こちらの想いを偏見なく受け取ってもらうには、それだけの負荷がかかりますが、その積み重ねこそが、信頼関係につながることを表している事例でもあります。店長の立場で、限りある資源である「時間」をコミュニケーション機会に充てる、すなわち「投資」をするには、それなりの効果を想定し、その実現に向けて必要な準備をする必要があります。そのことを意識してやっているかどうかだけでも、コミュニケーションの効果・効率は変わってきます。
いわゆる【戦略的コミュニケーション】です。そういうと、少し大げさと感じるかもしれませんが、実際私たちは、その戦略的コミュニケーションをお客様に対して日々実践していることに気づきませんか?
入店いただいたお客様に対し、売れる販売スタッフは、「限られた時間で~を紹介し、販売につなげるには?」と目的を設定し、お客様をよく観察し、状況に合った出方が柔軟にできるよう、日頃からコツコツ準備をしておき、言葉を選びながら、何をどういう順序でどう見せるかを考え、対応しています。だからこそ、短い時間でもお客様の心を開かせ、掴み、その気になってもらえる確率が高まるのです。
それと同じように、戦略的なコミュニケーションをスタッフに対して行うのが店長の仕事です。
店舗ビジョンをただ説明するのではなく、「店舗ビジョンを売り込んで、それに乗ります!という気持ちになってもらうには?」、相手の話を聞くだけでなく、「その奥にどういう本音が隠れていそうか?」を五感で探りながら対応法を考える、などなど、店長自身が接客で身につけてきたスキルを思う存分発揮することが風通しの良い店舗づくりにそのまま役立ちます。

もちろん、お客様とスタッフは違う。お客様は初回で対応する必要はあるが、スタッフは長年の付き合いで分かっていることも多い、という声もあると思います。しかし、人の心は常に揺れ動くもので、「知ったつもり」が一番怖いと言えます。昨日の自分と今日の自分でも考え方が変わることがあるように、スタッフもちょっとしたことで受け止め方が180度変わることはあります。だからこそ、日々アンテナを立てて観察し、短い時間でもやり取りすることで、その変化に早く気付いたり、対応ができたりします。
そういう意思疎通の基盤をないがしろにして、チームワークは育ちません。「声をかけ合おう」とよく言われますが、実はその効果は大きいのです。
以前目にしたハーバード大学の研究でも、「39%の回答者が、同僚に声をかけられ、仕事上のことであれ、個人的なことであれ、言葉を交わすときに最も強く帰属意識を感じると答えている。その結果に、性別や世代は関係なかった。回答者の世代を問わず、声をかけ合うことは、帰属意識を築くうえで最も一般的な方策だった。」という文言がありました。お金も時間もそうかからない方策ですから、今日から早速、”戦略的に”実践してみませんか?
★関連記事→あなたの店舗のチームワーク。スタッフはどう見てる?~スタッフの生の声から:ブランド店長問題解決講座(80)
★お勧め本→Kindle&ペーパーバック出版!【ラグジュアリーブランド店長として輝き続けるための 5つの問い】9月1日出版,『新しい店長のバイブル~業績を上げ続ける店舗はこうして創る!』(PHP)
★ラグジュアリーブランド研修についてはこちら→ラグジュアリーブランド研修シリーズ