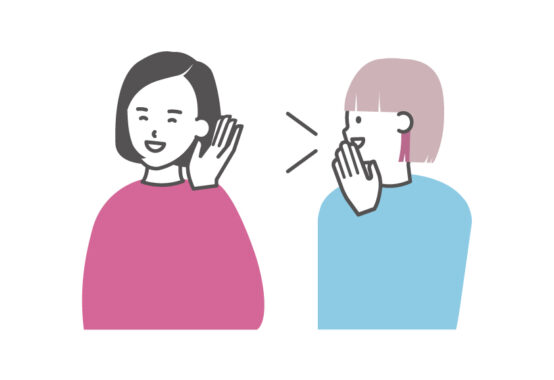■重要顧客が離れた!インバウンドの購入が減った!スタッフが退職!リスクだらけの毎日・・

今から振り返ると、私達はコロナを通じて貴重な体験をすることができました。コロナは中国・武漢で発生した後、あっという間に日本を含む全世界を巻き込み、ライフスタイルまでをも変えるというグローバリズムのインパクトを体感した時期でした。そして今、インフレで価格改定の波が押し寄せる中、円安の影響で世界各国から喜んで日本に観光に来られる人が以前よりも増え続け、日本エリアの売り上げだけは順調に上がってきました。こうしたことも踏まえ、世界は一時も休むことなく、日々目まぐるしく動いている、ということを店頭にいて感じている方も多いのではないでしょうか。
こうした環境変化自体を私たちはコントロールすることはできません。天気を自由に変えることができないように、為替も個々の力ではコントロールはできません。こうした変化は突然私たちに襲いかかって来て、店舗の売上にも大きなインパクトをもたらす事実がある一方、店長として安易にこの”環境変化”を売上が上がらない言い訳に使うと、残念ながらあなたの価値は下がり続けてしまうという難しさがあります。
たとえば、店長としてあなたが「雨が続いたから」「価格が上がったから」「インバウンドが減ったから」などを常に売れない言い訳に使っていると、関係者の目にどう映るでしょうか?実際に環境変化の影響を受けていたとしても、それだけを理由にしていることで、以下のことが起こり得ます。
・雨天続きだといって、同じ百貨店内のすべてのお店の売上が下がったの?
・商品の値上がりによって、同じブランドのすべての店舗で売上が下がったの?
から始まり、
・天気予報で、雨が続くぐらいわかると思うけど、何も対策をしなかったの?
・価格が上がったから売り上げが上がらないというのであれば、今後価格が下がらない限り、売上が上がる見込みはないってこと?
・インバウンドは不安定要素の一つだけど、それに頼り切っていたってことを自分で証明しているのと同じだな、など
要は環境変化に対し、なすすべはありません、と自ら能力のなさを露呈しているのと同じで、結果的に店舗全体の価値も下がるとともに、スタッフから尊敬されなくなるリスクを増大させているのです。
■企業は「環境適応業」!
会社経営も店舗経営も企業活動である以上、環境と向き合い、それにどう適応していくかの闘いです。それが腑に落ちている店長と、理屈ではわかっていても本当のところ踏ん張れない店長との格差は、特に今のような環境変化が目まぐるしい時代になればなるほど明らかになります。
たとえばコロナがお店を直撃した際も、複数の店長と話をしていると、「日ごろの考え方、行動の習慣の違い」がこういうときにこそ大きな違いとして明らかになるということが如実に感じとれました。
ある店長は「突然百貨店自体に人は来なくなり、接客回数も減って、うちだけじゃなく周りも大変。そんな中、どうしようもないですよね」と、目に見える事実をそのまま受け止めて、それ以上考えを発展させることもなく、ただただ悲観して終わっていました。
しかし”できる店長”はこう言いました。「イベントも中止になり、見込んでいた数字もとれていないという厳しい現実はあります。ただ、コロナ前まではインバウンド景気に頼りすぎていた面もあります。こういうことはこの先も当たり前に起こりうると思うので、改めて強い店舗を創るために何が必要なのかを洗い出しています。いつか事態は収まると思いますが、その時に“厳しい時期にこういうことをやっておいてよかった”と思える状況を創るために、時間を有効に使います」。
具体的に何にどう取り組んでいるのかを聞いてみると以下の回答が戻ってきました。
来店が少なく時間はあるので、今後立て直しのために何が必要かをスタッフと話し合って
*ローカル顧客の掘り起こし(以前購入のあった方を洗い出す)を徹底するという課題を設定しました。
ー連絡先が分かる方は、こちらからコンタクトをとる(「突然何?」と思われる可能性もあるので、まずは「ご無沙汰してしまいまして申し訳ございません。コロナになってお加減いかがでしょうか?ご無事でいらっしゃいますか?」という挨拶だけでOKとする)
ーその反応によってお客様の今の状態を把握する
*インバウンドで深く踏み込む接客ができていなかったことを踏まえ、再度顧客化のためのプロセスを研究し、トレーニングを実施し徹底させる
*効率化できるバックオフィス業務はないかを洗い出し、店頭集中体制をとる、それによって、突発的に欠員が出ても回せるようにする
などなど、要は厳しい環境に直面しても、いかにスタッフがプロアクティブ(能動的)に考え、動けるようにするかに注力し、そのための施策を考えて丁寧に手を打っていったとのこと。実際、それによってお客様から「電話もらえて本当に嬉しかった。また行くわ」というお声も複数いただけ、丁寧な接客で喜んでいただけて、お店の一体感も強化され、明るいムードになった、と話してくれました。
本部でも日々変化との格闘でなかなか行き届いたフォローができない中、益々このような戦略的な店長が必要とされている現実があります。
■どうすれば戦略的店長になれるの?

戦略的であるとはどういうことでしょうか?いろいろな角度で様々な定義が存在しますが、店長という立場で考えると
①常に自店の強みとチャンスを見つけようとしている
②そのためにも、競合を含む他店の情報や世の中の動き・流れに関する情報を積極的に得ようとしている
③ ①②から、今取り組むべき重要課題を絞り込んで、それをスタッフを巻き込んでとことんやりきろうとする
ということが必要と言えます。
裏を返すと、私たちは数字が思わしくないとつい、自店の「弱み」や「脅威」に目が行き、「うちでは~が足りないから・・」「~しようとしてもどうせできないから」という理由を考え、行動にブレーキがかかりがちです。戦略的な店長は、そういう時こそ「他店でできていなくて自店でできていること」「お客様が評価してくださっていること」「最近現れてきたポジティブな変化・動き」などを意識して注視します。なぜなら、良い芽を育てることこそが、リカバリーするうえで一番の近道になる上、モチベーションも維持できるからです。
また、どうしても数字が悪いと焦って「あれも、これも」と手を出しがちです。戦略的店長はあえてそれを我慢し「これに集中することで結果的に波及効果で~もできるようになる。だから、まずはこれにとことん取り組んで結果を出そう!」とリードします。その方がスタッフもわかりやすく、結果も出やすいことを知っているからです。
実際、ある戦略的店長は、「リカバリーのためにはセット販売率を伸ばすことが鍵」と課題を絞り込んだ後、はやる気持ちを抑えて、以下のことに取り組んで見事お店を復活させました。
a.「うちのお店はこれまでの傾向から、リピーターの方のセットでの買い上げ率が新規の方より●%も高いです。主な理由としては1回目よりさらに深くお客様とコミュニケーションがとれ、個別のお好みを踏まえたコーディネート提案ができていることが挙げられます。これは私たちの強みです。それをさらに伸ばしていくことで、売上アップと顧客化の両面を実現したいと考えています」
b.「ですからまずは既存のお客様には必ずセットでお勧めすることを徹底しましょう」
c.「そのためには、必ず担当のスタッフ+1名つく、を徹底します。なぜならお客様の傾向を見ると複数点買われている場合は担当スタッフと密に相談しながら~ができたから、というお声をいただいているからです。それに専念するのためには接客フォロー役が必要です」
d.「そのフォローのスタッフの役割としては、2つあります。この○○と△△を行うことで、成果につながります」
e.「そこで、フォローに入った後それをフィードバックしあい、より効果的・効率的な接客フォローの仕方をマニュアル化していきます」
f.「そのマニュアルに沿って動くことによって店舗全体のセット率を上げていきます」
g.「取り組む中でもっと良いやり方があればマニュアルは更新していきます」
h.「まずは準備期間として~をし、●月●日から●月●日までやって結果を検証しましょう!」
g.「最終的には誰もがスムーズなフォローをしあえてお客様に心地よくたくさんお買い物していただけるお店にしましょう!」
と、「それなら高い目標でも達成できそう」というストーリーを根拠をもって示し、且つそこからスタッフ自身の行動やアイディアを加味して成功につなげていました。
できる店長いわく、「”実際やってみないと成果につながるかどうか、本当はわからない”という気持ちもあるけれど、スタッフに「やる価値がありそうだ」と思ってもらうことで、動いてもらいやすく、結果も出やすくなります。逆境の時ほど、どのように行動し、スタッフのモラールをどう維持するかというリーダーの真価が問われます。どんな店長にも降りかかる厳しい状況は、精神的にきついということはありますが、中長期視点を持って着実にスタッフのスキルアップやチームの基盤づくり、そして何より店長自身のリーダーシップに磨きをかける重要な点検の時間として与えられていると思っています。」とのこと。その心構えと芯の強さにスタッフはついていくのだろうと素直に思えた出会いでした。
★関連記事→できる店長が実践している効果的なメッセージの伝え方とは?:ブランド店長問題解決講座(74)
★お勧め本→Kindle&ペーパーバック出版!【ラグジュアリーブランド店長として輝き続けるための 5つの問い】9月1日出版,『新しい店長のバイブル~業績を上げ続ける店舗はこうして創る!』(PHP)
★ラグジュアリーブランド研修の情報はこちら→ラグジュアリーブランド研修