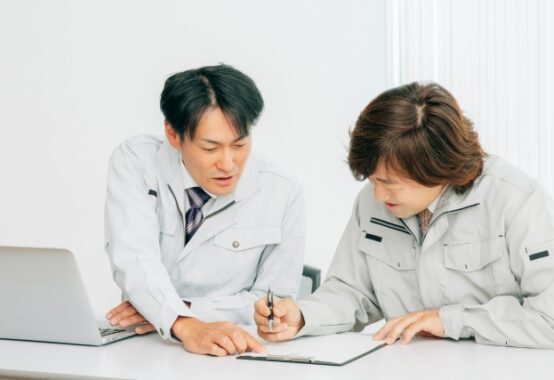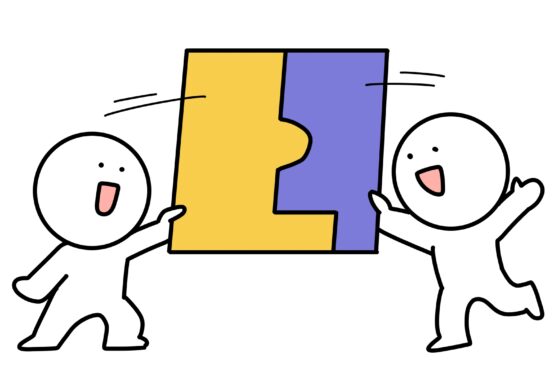■旅人化するZ世代新入社員
4月の入社時点では「頑張りたい!」という決意の一方、不安・緊張の表情が印象的な新卒も、店舗に配属されて3か月ほど経過すると、業務を一通り教わり、徐々に独りでやれることが増えてくるようになります。周りから見れば「たった3か月」かもしれませんが、本人たちにとっては”怒涛の日々”です。理由として、社会人、企業人、組織の一員という立場で、責任を感じつつも慣れないことばかり。必死についていこうとする反面、ミスもしてしまい、心の揺れが非常に大きい時期でもあります。学生時代(特に大学生)は大半のことを自分で計画でき、自分らしくいられた自由度の高い環境との対比で、入社後の様々な制約の中での日々は反動も大きいのかもしれません。配属された店舗にもよりますが、中には先輩が非常に忙しそうで、丁寧に教わることができない状況に置かれ「なんとなく自分がこの店にとって”よそ者”あるいは”厄介者”的な感じを受けてしまうが、自分からどう溶け込んで良いのか正直わからない。想定していた状況と違った」と訴える新人もいます。また、憧れをもって入社したものの、思った以上に自分ができないことが多く「早く精神的なゆとりが欲しい!」と焦る段階でもあります。そこを乗り越えて「頑張れた自分」を発見することが最初の成長課題ではありますが、売り手市場だけに、ふとしたことで「もしかしてここは自分には合っていないのかも・・・他に内定をもらった会社もあったけど、そっちの方が自分には合っていたのかも…」と考える人がいてもおかしくはありません。
さらに昨今は、育ってきた時代背景や環境の影響もあるのでしょうか。従来と比べると”繊細だな”とこちらが感じてしまう人が増えており、実際、研修時に「ビジネス基礎意識調査」を行うと、リスクを冒してでもチャレンジするというより、失敗しないように慎重に対応する、という守りの姿勢が強い傾向がうかがえます。
ゆえに、同じ失敗体験や同じ指摘や注意でも、その受け止め方においては、思ったより何倍も落ち込んだり、気にして引きずるという傾向も強くなっています。
そういう体験が重なると、「せっかく入社したのだから、奮起して頑張らなければ・・」という考えよりも「みじめな自分でいたくない」という感情の方が優先し、会社に行きたくない、と心だけでなく体も拒絶反応を起こし始めるケースも発生します。
その気持ちを放置すると、そのうち「考えてみたら、そもそも入りたい会社じゃなかったけど、皆がいいと勧めるから・・」「会社説明会で言われたことと実態が違った、早く見切りをつけた方が、時間を無駄にしなくてよい」などの合理化が始まり、徐々に「自分がその会社・店舗にいる意味・意義が見えない」「空しいまま時間を使っているのはもったいない」という気持ちが渦巻いてきます。
かくして、「今ならまだやり直しがきく。新しいステージを探そうかな・・・」という誘惑が頭をもたげはじめるのです。
そこを待ち構えているのが“エージェント”と言われる人材あっせん会社で、魅力的なキーワードでよその世界への扉を開ける後押しをしてくれます。「第二新卒」という市場も引く手あまたであり、従来に比べると流動化する誘因も多いのが実情です。

要するに「真っ白だからこそ、自社のDNAを素直に引き継ぎ、将来的に会社を担う人材になってほしい」と、せっかく採用経費をかけ、吟味をして採用した新卒であっても、根底では「旅人化」が急速に進み、配属された先での仕事や人間関係を含めた環境に価値を感じなければ、簡単に次の場所を探して旅に出てしまう、という状況があります。
では、それに対して、会社・店舗として何ができるのでしょうか?

■Z世代新卒の土台作りには1.5倍のエネルギーを!-メンター育成のチャンスにつなげるには?
「辞めていくのは仕方がない」と言っていると、人手不足が慢性化し、あちらこちらにしわ寄せがくるという悪循環が待っています。一方の先輩たちも人手不足の中、生産性を問われ、業務に追われる中で、新卒をどう育てればよいのでしょうか?
そこで求められるのが、店長の「中長期・大局的視点」に立った、新人育成体制・風土づくりの推進力です。
新卒が入ってくるということは社会人としてのマナーも含め、ゼロから教えなければならず、負荷も大きくかかります。
しかし、見方を変えれば「指導スキルを持った人材の育成=人を育てる風土づくり」に取り組むことで、関係者全体のメリットにもなるうえ、今後のさらなる環境変化にも柔軟に対応できる力をつけられるチャンスにもなります。
目先の売り上げも大切ですが、業績を上げ続けることが店舗のミッションであることを考えると、新人育成を片手間仕事ではなく、「戦略的課題」と位置付けて成功確率を高めることが重要です。
ある店長が大切にしているのは、「最初の刷り込みと言われても、何を刷り込むかが重要です。私自身、ラグジュアリーブランドブティックの一員としてのあるべき姿をもとに、到達してほしい基準を決めており、そのためにもまずは足元で”許すことと許さないこと”、新人から見れば”許されることと許されないこと”とその理由を明確に教え、それはしっかり守ってもらいます。守れなかったときは、放置せず、なぜできなかったのか、次からできるようにするには何が必要かを良い教育チャンスとしてしっかり向き合います」ということ。
たとえば、姿勢においてもお客様からご覧になって背筋が伸びて美しい姿勢になるよう、まずは鏡を見て練習してもらいます。そこで1つの型を確認し合い、それが崩れている時には、崩れていますよ、とフィードバックします。習慣になるまでは何度か言わなければいけないのですが、事前にすり合わせている分、修正も早いです。指摘されて、本人が「あ」と気づいて直して、を数回繰り返すうち、言わなくてもできるようになり、それがその人の価値を高めます。その他の業務においても、「どんなに忙しくてもダブルチェック」など、重要項目においては徹底を促します。中には「そこまで細かく言われるのか」と思う人もいますが、「必ずそれがお客様、店舗、あなたのプラスになる」と言い聞かせ、定着させます。すると、後輩が入ってきても、自分が新人の頃言われたことはきちんと指摘しています。それが良い指導になっています。
また、店長が新人を細かく指導する余裕がないこともしばしばあるため、重要なのはメンターと言われる育成のメイン担当になったスタッフの役割です。
行き当たりばったりではなく、店長と何をどのレベルまでできるように指導するかについて確認し合ったうえで、受け入れた新人個々の強み・弱み・理解度に沿って育成計画を立てます。それを着実に遂行することで、新卒だけでなくメンターにとっても成功体験を積ませることが大切です。
新卒にとっては、上司・先輩の元で仕事をするという「縦社会」がほぼ初めてなだけに、身近に相談しやすい先輩をメンターとして機能させ、メンター自身にも育成力をつけさせるチャンスにするのです。
メンターのちょっとした対応によって新人の意欲や成長度合いは大きく変わってくることを考えると、まずは、そのメンターの育成スキルの向上を促進するのが店長の仕事と言えます。

「あのお店は新人が良く育つ」という評価を得ているある店長に話を聞くと、以下の6つのことに気を配っているとのことです。
①事前にメンターと店長で新人の育成計画(いつ、だれが、何を、どのレベルまで教えていくか)を立てる。ただ、全スタッフを巻き込むために、各自に何らかを教える役割を振り、共有しておく。
②新人が配属されたら、メンターと新人で目標・計画を共有し、週に●回など、定期的に進捗を確認しあう体制にし、必要に応じて目標・計画の軌道修正を行う。
②先輩のやり方のばらつきがあり、新人に混乱が生まれる恐れがある場合は、店長も入ってどれが最も効果的・効率的かを考え、統一した業務フローをその都度確認する。
③メンターが新人にホウレンソウのルール(どのタイミングで、何について、誰にどのように報告するか)を徹底させ、習慣化させる。
④メンターが新人に指示を出す際は、業務の目的・理由を伝えたうえで、具体的な手順を教えてやらせる。また、タイムマネジメントを実践させる。その際、相手の理解度に合わせて必要なら3回言い方を変えて伝える、指示する。また、理解度・定着度を確認するやり方を複数用意しておく。(クイズ、ロールプレイングなど)
⑤メンターに限らず、店長及び先輩社員全員が普段から新人の仕事ぶり、態度、行動について具体的な根拠をつけて直接・間接的にフィードバックするよう促す。
⑥日ごろから質問形でコミュニケーションをとっていく。(ex.今回うまくいった理由は?・・)
実際に前向きに上記のことにしっかり取り組んだ店舗では、1年たつとメンター側から「難しさもありますが、人が育っていくのを実感できて、マネジメントにぐっと興味がわいてきました」「自分にとっても業務の棚卸になり、効率がアップしました」「新人が入ってきたら皆で協力して育てる、がうちでは当たり前の空気になっています」という声が聞かれ、一石5鳥、10鳥につながっています。確かに店長、メンターだけでなく店舗全体にとって、「見て、盗んで、学べ!」という昔の育成法に比べるとその1.5倍は丁寧に手をかけて育てないといけない状況にはなっています。が、手をかけた分、新人や協力しあう上司・仲間に対する愛着や一体感も生まれ、新人が育って生き生きと仕事をするようになった姿を見る時の喜びも1.5倍、あるいはそれ以上かもしれません。
★関連記事→Z世代が求める価値ある接客サービスとは?~一客入魂~:ブランド店長問題解決講座(75)
★お勧め本→Kindle&ペーパーバック出版!【ラグジュアリーブランド店長として輝き続けるための 5つの問い】9月1日出版,『新しい店長のバイブル~業績を上げ続ける店舗はこうして創る!』(PHP)
★ラグジュアリーブランド研修の情報はこちら→ラグジュアリーブランド研修